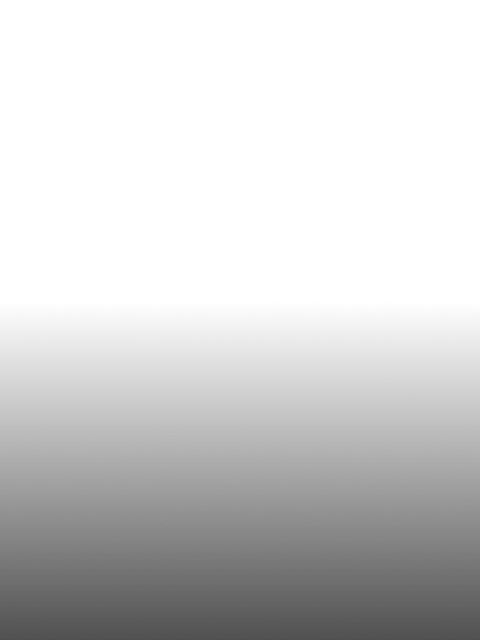ウォルト・ディズニーの約束 メアリー・ポピンズは誰のために舞い降りたのか
威厳ある頑固な中年英国婦人役に、今トンプソン以上の適役はいない。そして子どもたちにそんな英国婦人のイメージを作り上げたのはメリー・ポピンズかもしれない。映画のポピンズは朗らかさもあるけれど、原作ではもっと不機嫌で手厳しい。本作は映画と原作の間を行き来しながら、原作者トラヴァース夫人がどのようにポピンズを作り上げたか、それをディズニーがどのように映画用に脚色していったか、二人の間のバトルと、その理由になったトラヴァース夫人のトラウマを解き明かす部分でできあがっている。
ポピンズは子どもたちの書いたこんなナニーにきてほしいという手紙を手にやってくるのでてっきり子どもたちを助けるために来たのだと、それはウォルトじゃなくても思うところ。が、そこにおそらく夫人自身も気がついていなった亡き父の人生へのトラウマがあることにウォルトが気づく。それによって映画「メリー・ポピンズ」が誕生し、トラウマから解放され、自分の創作意欲を再発見した夫人もポピンズを書き続けられた、とエピソードを重ねて描き出す。
ドラマは娘と父の葛藤と、原作者と映画人たちのバトルで出来上がっているけれど、ここにミュージカル映画の傑作ソングである挿入曲の誕生などのエピソードを加えバック・ステージ物としても楽しめるように作られているのが楽しい。
役者たちもいい芝居をしているのにオスカーに無視されたのは、ウォルト・ディズニーがユダヤ嫌いだったからだとはもっぱらの噂である。
posted by
まつかわゆま
0 comments
シネフィル アジア
シネフィルアジアは、日本を中心とした映画ファンが自由に映画の事を
語り合える場所です。
新作映画の情報、監督インタビュー、国内外の映画祭の情報など、
デジタルマガジンとしても楽しめます。
映画ファンと映画関係者が集い、チケットプレゼントなども
用意して、誰もが映画を楽しめる環境と話題を提供していきます。


 *REVOLVER
*REVOLVER