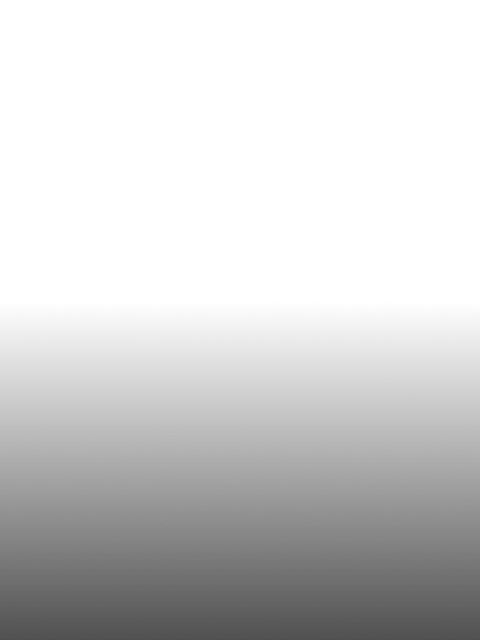映画は音楽だ! 『2001年宇宙の旅』(68年) ♫ヨハン・シュトラウス「美しき青きドナウ」
(16:9) One scene from great sci-fi movie. Now in 16:9 and with original music. Stanley Kubrick 1968, 2001: A Space Odyssey Music: Johann Strauss, The Blue Da...
1990 年代、月に一度はアメリカへジャンケットなるものに出かけた。いうなれば、映画の監督や出演者の取材である。ロサンゼルスへ行くお楽しみといえば、ハリウッドにある書店めぐりだった。ここでは、日本では売ってないような映画用スクリプト (台本) が売っていた。シナリオライターのための勉強用教材だった。
『ゴッドファーザー』(72年)や『許されざる者』(92年)など、ぼくが大好きな映画はほとんど買った。いまはインターネットでも見られるので、躍起になって集めていないが、それらの脚本を英語で読むのが何よりの映画の勉強であった。
スタンリー・クブリック監督の1968年のSF映画の金字塔的作品『2001年宇宙の旅』(68年)には、クラシックの名曲が数多く使われている。リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラかく語りき」やリゲティの「アトモスフェール」や「レクイエム」なども印象深いが、何よりも円舞曲「美しき青きドナウ」 が忘れがたい。スペースシャトル、アリエス1B型 (宇宙ステーションと月面を往復するスペースシャトル、「宇宙の荷馬」というあだ名を持つ) が月に向かうシーンと、超重要な最後のエンドクレジットで流れるのだから。
その月に向かうシーンの前のシークエンスで、棍棒は人類が歴史上初めて手にした武器で、モノリスの進化に促された猿人たちは骨製の棍棒を手にする。猿人たち がそれを天空高く放り投げると、場面が変わって、宇宙船に変わるというわけだ。そこでズンチャチャズンチャチャとウィンナー・ワルツが流れた。まるでヒトが作ったすべての道具は棍棒の延長線にほかならない、といっているかのようだ。
前述したスクリプト (英語版脚本) をひもとくと、「Thousand Megaton Nuclear Bomb in Orbit above The Earth」とト書きにあって、なんと猿人がほおった骨は単なる「宇宙船」でなくて、「核ミサイル搭載の軍事衛星」だったことがわかる。
パンアメリカン航空 (1991年倒産して運航停止) をはじめとするアメリカ、フランス、ロシア、中国など世界各国のスペースシャトルや人工衛星が宇宙空間を飛び交っている。そこで底抜けに明るい「美しき青きドナウ」が流れれば、何か平和利用の延長線上の出来事であるような錯覚を持つけれども、実際は相当に「物騒な世界」になっていたのである。
「美しき青きドナウ」は、ヨハン・シュトラウス2世が1867年に作曲した管弦楽用ワルツ。
1966 年の普墺戦争に敗北し、失意のどん底にいたウィーン市民の心を癒すために作曲された。当初は男声合唱曲として作曲され、「くよくよするなよ!」や「悲しいのかい?」といった歌詞が図星にウィーン市民の心情を吐露していたため、反響はあまり好ましいものではなかったが、管弦楽曲に書き直されて人気を博し、 「オーストリア第2の国歌」「ヨハン・シュトラウスの最高傑作」とまでいわれた。
曲は弦楽器のトレモロに乗ってホルンが静かに主題旋律を奏して、ドナウ川の源流にあたる「ドナウの泉」や「黒い森」の情景が描かれる。次第にワルツに発展し、ニ長調の主部となる。その後、明るい5つのワルツが連結され、主部となり、華々しいコーダとなって終わる。演奏時間は約10分。今では、ウィーン・ フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤー・コンサートのアンコールの定番曲としても知られている。
2001年段階で、映画のように人類は月面にまだ住んでいない。『2001年宇宙の旅』の公開は1968年で、アポロ11号乗組員が月面に立つのは1969年7月20日のことだ。それを思うと、クブリック監督の壮大なイマジネーションに驚くばかりだ。
近未未の宇宙空間で世界各国の核兵器が飛び交う恐ろしい世界を現出させたのは、冷戦下の『博士の異常な愛情』(64年)のラストでキノコ雲を見せた皮肉屋クブリックらしい。
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER