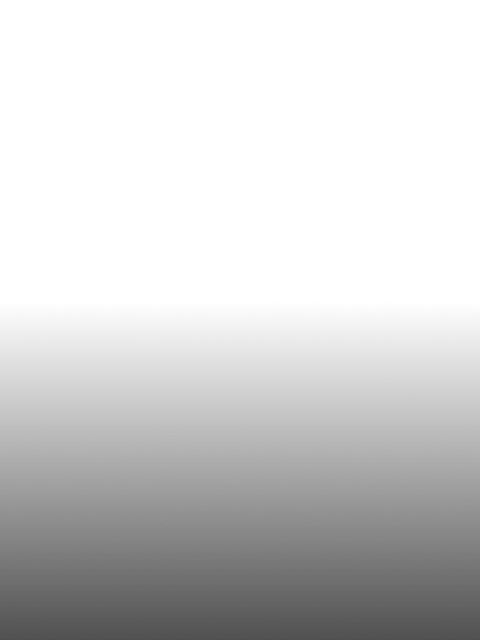イーダ : 映画評論・批評 - 映画.
2014年8月2日よりシアター・イメージフォーラムにてロードショー
美しい構図の陰で過去が発掘され、苦痛が変容していく
四角い黒白画面の下部に人物の姿が沈められている。頭上には大きな空白が生まれる。まるで教会の内部にいるように見えるが、そうとは限らない。他の空間でも、この構図はしばしば出現する。それも固定ショットで。
すると、人物が小さく見える。小さいだけでなく、ぽつねんとした感じが漂う。身体と心の関節がどこかで大きく外れている。
イーダ(アガタ・チュシェブホフスカ)は最初、アンナと呼ばれている。18歳の戦争孤児で、ほどなく修道女になる予定だが、音信不通だった叔母ヴァンダ(アガタ・クレシャ)に会うと「イーダ」と呼びかけられる。イーダとはユダヤ人の名前だ。1962年、社会主義時代のポーランド。50年代初頭、叔母は人に恐れられる検察官だったが、いまは酒と煙草と束の間の情事に逃げ込んでいる。
そんなふたりが4日間の旅に出る。イーダの両親が命を奪われた経緯を探りにいくのだ。無垢で信仰心の厚い少女と、シニカルで無神論者の中年女。過去は発掘されるのか。ふたりの女が抱える不穏や苦痛は変容するのか。
監督のパベウ・パブリコフスキは、ドライヤーやブレッソンを思わせるタッチで、80分間のロードムービーを織り上げる。構図の美しさで観客の眼を惹きつつ、登場人物への感情移入を禁じつづけるのだ。抑制されたこの距離感が、ふたりが行動する小宇宙の後背地を際立たせる。そんなキャメラが映画の終盤、急に移動しはじめる瞬間は見逃さないでいただきたい。たとえかりそめの解放であれ、外気を胸に吸い込んだイーダは、新たな受難を恐れぬ覚悟を定めたのではなかったか。
(芝山幹郎)
- 映画.com
http://eiga.com/movie/79411/critic/
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER