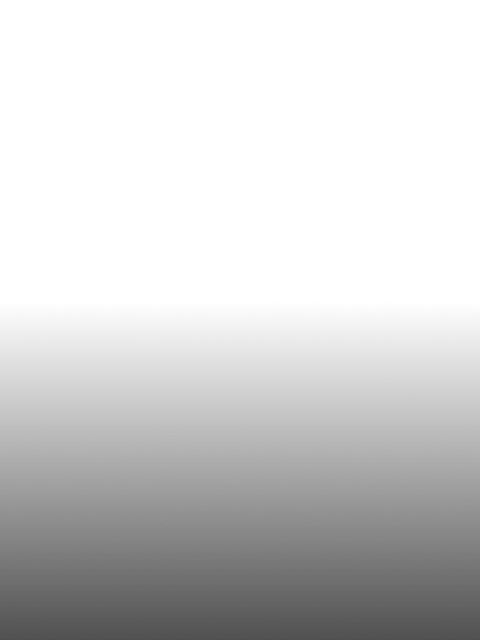サトウムツオ「映画は音楽だ!」第4回はゴダール監督の名作。
『勝手にしやがれ』(59年)
♫モーツァルト「クラリネット協奏曲イ長調K.622」
1959年のジャン=リュック・ゴダール監督の長編デビュー作『勝手にしやがれ』(原題À bout de
souffle)は仏ヌーヴェルヴァーグの記念碑的作品で、ジャン=ポール・ベルモンドとジーン・シバーグが主演している。
フランスのマルセイユで自動車を盗んだミッシェル(ジャン=ポール・ベルモンド)は追ってきた警官を射殺する。パリにたどり着いた彼は、アメリカ人のガールフレンド、パトリシア(ジーン・シバーグ)と行動をともにする。ハンフリー・ボガートを気取って何かの映画のボガートの仕草を真似て、唇を親指でなぞる仕草をするミッシェルは相当なボガートファンらしい。だが、パトリシアはミッシェルが警察に追われる身であることに気づいてしまう。やがて心変わりしたパトリシアが警察に密告してしまう。警察が銃が火を吹く。ミシェルは背中を撃たれ、よろめきながら大通りにたどり着き、前のめりなって倒れる。「俺は最低だ」とミシェル、「最低って何のこと?」とパトリシアがボガートの真似をして唇を親指でなぞり、そうつぶやいて終わる。
パリのシャンゼリゼ通りで『ニューヨーク・ヘラルドトリビューン』紙の売り子をしていて、その新聞社の黄色いTシャツを着て登場するジーン・シバーグが圧倒的に可愛い。髪はオットー・プレミンジャー監督の『悲しみよこんにちわ』(57年)から抜け出たようなベリーショート「セシルカット」で、大柄のストライプのワンピースを着たり、完全にファッションアイコンとなっている。
このジャン=ポ=ル・ベルモンドが演じるミシェル・ポワカールの生き様が刹那的でたまらなく好きだ。愛した女のパトリシアは曖昧な欲望しか持てぬプチブルジョアで、実はつまらない女であった。ここが悲しい。彼女を愛したがゆえに彼は死ぬ運命にある。
ゴダールは1960年に、仏『ル・モンド』紙のインタビューに次のように答えている。
「私は、トリュフォーの主題から出発してアメリカ女とフランス男の話を物語ったわけです。ふたりの仲はうまくいかない。男のほうは死について考えているの
に、女のほうは死なんか考えないからだ。私はこのアイデアを持ちこまない限り、映画がおもしろくなるわけがないと思った。青年の方はかなり前から死ぬこと
ばかり考えている。死ぬことを予感している青年。そういう考え方から、青年が街頭で事故死を目撃するシーンを撮った。同じ理由で、レーニンの言葉、《われ
われは賜暇中(しか。官吏などが願い出て休暇を許可されること)の死者である》を引用し、モーツアルトが死の直前に書いたクラリネット協奏曲を使っています」
この映画で逃避行をしていたふたりはアントニオ(アンリ=ジャック・ユエ)という友人の紹介で女の家に行き、そこを隠れ家とする。その隠れ家で、ウォルガング・アマデウス・モーツァルトの「クラリネット協奏曲」をレコードでかけて、主人公ミシェルに「好きだ」とまでいわせているのだ。
クラリネット協奏曲イ長調K.622は、ケッヘルの番号が大きいことからも分かるように、死期の近いモーツァルト最晩年の、1971年に作曲されたクラリネットと管弦楽のための協奏曲だ。ケッヘルの比較的大きい「レクイエムニ短調K.626」や「歌劇『魔笛』K.620」と比較すると、そこに死の匂いをまとっていることが分かるはずだ。モーツァルトの「クラリネット五重奏曲イ長調K.581」と同様に、当時ウィーン管弦楽団のクラリネットとバセットホルンの名手だったアントン・シュタードラーのために作曲したもので、低音が出せるバセット・クラリネットのためにと作曲された。今の楽譜では、A管クラリネットによって演奏できるように、何者かが編曲したものだ。
『勝手にしやがれ』では、3楽章あるうち第2楽章などが使われていた。簡素で味わい深く、比類なく美しいメロディは、デンマークの作家イサク・ディ=ネセンの小説『アフリカの日々』の映画化で、シドニー・ポラック監督、メリル・ストリープ&ロバート・レッドフォ=ド共演のアカデミー賞7部門受賞作『愛と哀しみの果て』(85年)のアフリカの情景と実にマッチしていた。
http://youtu.be/6QAAZ29cvfU
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER