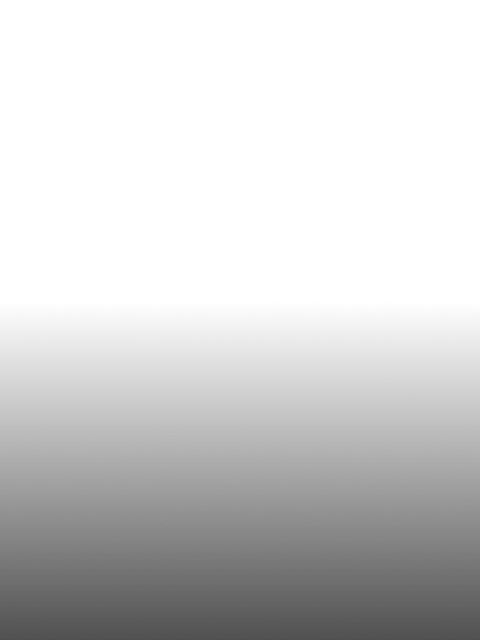Cinefilasia ショート・レビュー『蜩の記』
『蜩の記』
『蜩の記』は、品格のある作品だ。
品があると言う言い回しは褒め言葉ではあるが、昨今の日本人が忘れてしまった価値基準となってしまっている。この映画の主人公達は、死をも昇華して、生きていく意味を私たちに示している。
第146回直木賞を受賞した葉室麟の小説を、「雨あがる」「博士の愛した数式」の小泉堯史監督のメガホンで映画化した時代劇だ。
もちろん、小泉堯史監督ならではの、黒沢組のスタッフによる、完成度の高い、安定感のある映画製作がなされていることにも起因している。
主演の十年後に切腹を言い渡された戸田秋谷役、役所広司を中心に、岡田准一や原田美枝子、堀北真希らの演技もよかった。なかでも、やはり役所広司と原田美枝子がすばらしい。控えめだが存在感のある演技をしている。
主人公の死に向かう時間に寄り添うように、日本の美しい四季が描かれる。武家らしい、つつましやかな生活のなかで、一日一日を丹念に生きていく。
諺の「柚子は九年で花が咲く」ということばについて、原作者・葉室麟は次のように語っている。
「人生の後半で何事かをなしとげたいと思った人間にとっては「花」という言葉が若いときよりも心に染みます。
「蜩の記」は人生の残り時間を限られた人間の物語です。
人生の時間を砂時計の砂が落ちるように見つめています。
この映画は私が九年待った柚子の花であることをお伝えしたいと思います」。
この柚子の花は、主人公の家の庭に植えられている。小泉監督が作者の人生の感慨を汲み取って、映画に登場させたのだ。
後半の場面で見せる、出発する主人公と、それを見送る家族が心に残る。
主人公は人生が集約されたような、迷いのない笑顔で、家族に別れを告げる。家族との惜別の場面で、その表情には清々しささえ感じた。
夫婦、家族や子弟の愛とともに、人生をまっとうに生ききった主人公の姿を、描き出す。
生きる事、死ぬ事を通して人生の品格を描いた映画だ。
主人公の死に向かう時間に寄り添うように、日本の美しい四季が描かれる。武家らしい、つつましやかな生活のなかで、一日一日を丹念に生きていく。そこには、今はもう失われてしまった、日本の生活がある。
(シネフィルアジア編集部)
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER