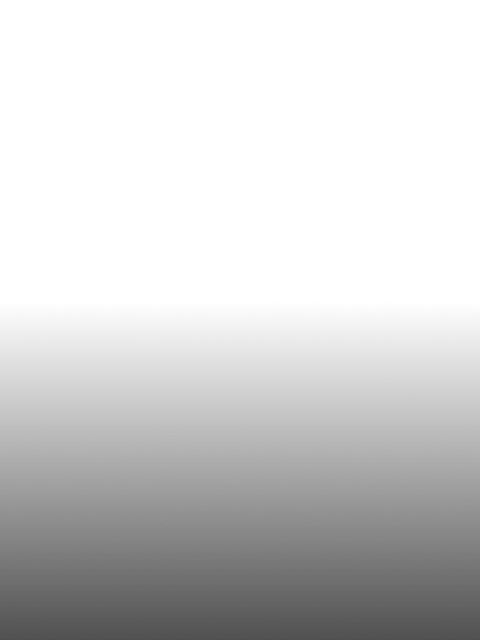映画監督・旦 雄二の ☆ それはEIGAな!
第16回 フランス映画社よ、ありがとう!
1971年、大学1年の初夏。映画を、観たり撮ったりするだけではなく、上映するということもやってみたくなり、のちに日大から篠田 昇たちが大挙押しかけ『ハードボイルド・ハネムーン』を観せてくれることになる学内最大の教室を、ひとりで借り切った。上映する作品は、そのころまだあまり鑑賞できる機会がなかった、ゴダールの『イタリアにおける闘争』と決めた。まず自分が観たかったし、人にもぜひ観ていただきたい作品だったからだ。
西の郊外の大学から時間をかけて都心に16ミリ・プリントを借りにうかがった先の配給会社は、『フランス映画社』といった。その名が持つ洒落たイメージからはほど遠い、雑居ビルの地下の、狭く、薄暗い、机に書類や雑誌が山積みになった、雑然としたオフィスだった。しかし、それは、たまらなく素敵に思えた。こういう地道な仕事が映画を支えているのだと思った。
プリント貸出料は、たしか五万円だっただろうか。自分で映写し、けっこうな入りとなった観客(学友たち)にももちろんカンパを募ったが、到底 回収はできなかった。大幅に自腹を切る羽目となった。これで儲けるつもりも、配給の道に進む気もなかったが、映画を配給して上映してくださるプロの皆さんのご苦労、大変さを、はじめて知ることとなった。
フランス映画社にプリントを返却にうかがった際も、お借りしたときと同様に 柴田 駿さんが応対してくださった。いや、いずれの場合も柴田さんお一人しかおられなかった。そのつど柴田さんは、どこの馬の骨とも知れぬ映画青年に時間を割いてくださり、夢見るような目で映画談義をしてくださった。映画というもののスタートからゴールまでのプロセスのうち、最終局面の、じつは最も困難であろう配給上映の仕事を、少年のように嬉々として引き受けておられる、その学者然とした柴田さんは、ただちに私のリスペクトの対象となった。
そののちフランス映画社が始めたBOWシリーズも驚きだった。“この映画を日本で観られるとは!”という感激の連続だった。いずれもありがたく拝見し、多くのものをいただいた。
そのフランス映画社が、さきごろ倒産したという。あまり話題にはならないが、これは激震というべきだろう。多くの意味を持つ象徴的な出来事である。そもそもフランス映画社とBOWシリーズがなければ、この国のいまの映画シーンは まったく違ったものになっていたことだろう。はたして、ここまで豊かで深いものになっていただろうか。ここ数年の、これまでミニシアターと呼ばれてきた上映現場での作品ラインナップの変容、つまり本来のアートシアター的な役割をなかなか果たせなくなりはじめている現状を見るにつけ、そのことをあらためて強く思う。
フランス映画社よ、ありがとう。形を変えてでも、フランス映画社のなんらかの再起、復活を、こころより願うものである。
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER