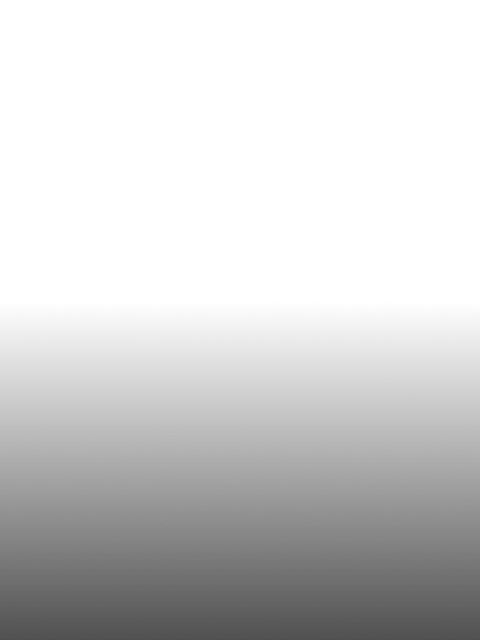「イマジン」 「音」、に注「目」するということ
いくつかの映画祭で一次審査に加わっている。日本の作品を見ているとプロが応募してくるものはさておき、どうも「音」についてのいい加減さが目に、いや、耳につくことが少なくない。
フィルムの場合、音は後からつけるものであった。同時録音で現場の音を取っておいても、それは音素材の一つであり、それを調整してセリフと合わせ、さらに作られた音を加えて映画の音は出来上がるものだった。
しかし、デジタル機材が発達し、その機材で撮られた音も十分に使えるレベルのものになったとき、つい、音は映像と対になっていると安心してしまい、音をどう使うかを考えずに作品化してしまうのである。
音は一つの表現を持つ素材である。どこに、どんな音を使うか、それはどのくらいの大きさで、どこから流れてくるのか。その音が「表すもの・こと」は何なのか。それを考えて作られた映画は、厚みが違う。それは劇映画だけではなくドキュメンタリー映画でも同じである。この話はまたいつかしよう。
さて。こんなことを考えたのは『イマジン』という作品を見たからだ。
『イマジン』は盲目の子どもたちが学ぶ学校にやって来た「反響定位」法の教師と子どもたちや若者、そして引きこもっていた盲目の女性との交流を描く。ラブ・ストーリーでもある。子どもたちは実際に目が不自由な素人をキャスティングしており、各国から集められた子どもたちは、英語・フランス語・ポルトガル語を話している。「反響定位」法とは、物・人・自分が出す音とそれが反響する音を聞いて自分の位置を知ったり物や人の位置を知ったりするという方法である。この方法を身につければ、白杖を持たずに外出することもできる、という。特殊な才能ではあるが、訓練を積めばある程度は取得できる方法でもあるらしい。しかし、日本など多くの国では、視覚障碍者が白杖を持たないで外出をすることは本人にとって大変危険であるということで禁止さえされているのが実情である。
舞台になっているのはポルトガルの視覚障碍者のための診療所で、監督はポーランド人。主役の男性教師はイギリス人俳優でヒロインはドイツ人女優である。共通語として英語のセリフが多いが、この映画の場合、大切なのはセリフや言葉より「音」なのだ。それを際立たせるためもあっての多国籍化ではないかと思う。
そう気づけば、あとは耳を澄ますしかない。観客にはすべてが見えている。そう思うのが、映画のマジックの一つである。登場人物の知らないことも観客には知らされているので、観客は登場人物たちの先回りをしてハラハラすることを楽しむのが古典的映画のセオリーの一つだ。
そのマジックを『イマジン』は引きはがす。観客も登場人物と一緒になって、あらゆる「音」を聞き、想像していかなければならない。そうでないと真実には到達できないのである。澄ますのは耳だけではない、観客には感じることのできない、匂いや太陽の温かさにも敏感にならなければいけないのだ。登場人物が感じているたろう現象を、観客は映像をもとに想像しなければいけない。そうして初めて「見えてくる」のが『イマジン』という映画である。
「音」というものの情報量の豊かさ、種類の豊富さ、意味などをこれだけ豊かに使って聞かせて見せた映画も少ない。そのアイデアに、まだまだ映画ができることは多いのだと気づかされもする一本である。
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER