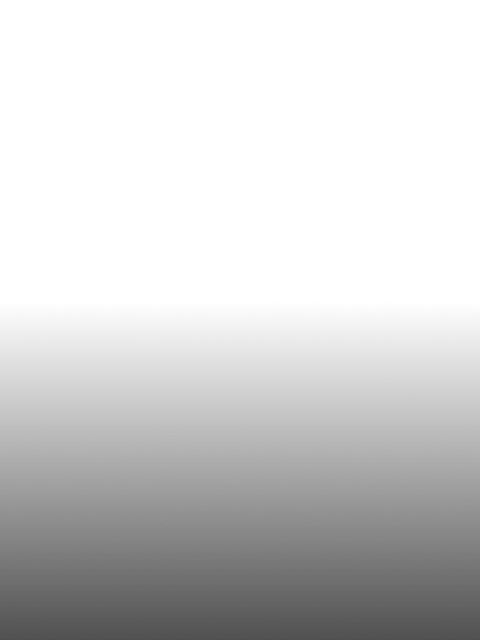利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはシネフィル アジアへのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。


いくつかの映画祭で一次審査に加わっている。日本の作品を見ているとプロが応募してくるものはさておき、どうも「音」についてのいい加減さが目に、いや、耳につくことが少なくない。 フィルムの場合、音は後からつけるものであった。同時録音で現場の音を取っておいても、それは音素材の一つであり、それを調整してセリフと合わせ、さらに作られた音を加えて映画の音は出来上がるものだった。 しかし、デジタル機材が発達し、その機材で撮られた音も十分に使えるレベルのものになったとき、つい、音は映像と対になっていると安心してしまい、音をどう使うかを考えずに作品化してしまうのである。 音は一つの表現を持つ素材である。どこに、どんな音を使うか、それはどのくらいの大きさで、どこから流れてくるのか。その音が「表すもの・こと」は何なのか。それを考えて作られた映画は、厚みが違う。それは劇映画だけではなくドキュメンタリー映画でも同じである。この話はまたいつかしよう。 さて。こんなことを考えたのは『イマジン』という作品を見たからだ。 『イマジン』は盲目の子どもたちが学ぶ学校にやって来た「反響定位」法の教師と子どもたちや若者、そして引きこもっていた盲目の女性との交流を描く。ラブ・ストーリーでもある。子どもたちは実際に目が不自由な素人をキャスティングしており、各国から集められた子どもたちは、英語・フランス語・ポルトガル語を話している。「反響定位」法とは、物・人・自分が出す音とそれが反響する音を聞いて自分の位置を知ったり物や人の位置を知ったりするという方法である。この方法を身につければ、白杖を持たずに外出することもできる、という。特殊な才能ではあるが、訓練を積めばある程度は取得できる方法でもあるらしい。しかし、日本など多くの国では、視覚障碍者が白杖を持たないで外出をすることは本人にとって大変危険であるということで禁止さえされているのが実情である。 舞台になっているのはポルトガルの視覚障碍者のための診療所で、監督はポーランド人。主役の男性教師はイギリス人俳優でヒロインはドイツ人女優である。共通語として英語のセリフが多いが、この映画の場合、大切なのはセリフや言葉より「音」なのだ。それを際立たせるためもあっての多国籍化ではないかと思う。 そう気づけば、あとは耳を澄ますしかない。観客にはすべてが見えている。そう思うのが、映画のマジックの一つである。登場人物の知らないことも観客には知らされているので、観客は登場人物たちの先回りをしてハラハラすることを楽しむのが古典的映画のセオリーの一つだ。 そのマジックを『イマジン』は引きはがす。観客も登場人物と一緒になって、あらゆる「音」を聞き、想像していかなければならない。そうでないと真実には到達できないのである。澄ますのは耳だけではない、観客には感じることのできない、匂いや太陽の温かさにも敏感にならなければいけないのだ。登場人物が感じているたろう現象を、観客は映像をもとに想像しなければいけない。そうして初めて「見えてくる」のが『イマジン』という映画である。 「音」というものの情報量の豊かさ、種類の豊富さ、意味などをこれだけ豊かに使って聞かせて見せた映画も少ない。そのアイデアに、まだまだ映画ができることは多いのだと気づかされもする一本である。
アカデミー助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズ。スキンヘッドにムキムキ筋肉の腕、逆三角体型に、黒のシャツとジャケット。とても音楽大学の教師とは思えないキャラクターつくりなのだが、彼の登場シーンみっつめでその理由がわかる。 『セッション』は『フルメタル・ジャケット』なのだ。シモンズ演ずるフレッチャー教授はハートマン軍曹なのである。監督もそのつもりで描いたという。なるほど、そのあたり、若い監督はバレバレに作っちゃうのだな。 サンダンスでグランプリや観客賞を獲った作品はカンヌのある視点部門か監督週間に登場するのが常なのだが、サンダンス映画祭ダブル受賞の『セッション』も当然カンヌで上映された。が、残念ながら見逃していたんだよね。で、メイン・コンペの『フォックス・キャッチャー』を見て、スティーブ・カレルのアカデミー賞”助演男優賞”を確信したわけだ。ま、色気を出して”主演”ノミネートにした時点でそれはちと無理、とは思ったが、「助演だったらとれたのに…」と私はまだ自分の予想に未練を持っていた。『セッション』を見るまでは。 J・K・シモンズはすごい。すごかった。助演男優賞ノミニーには『バードマン』で主役を食ってしまってマイケル・キートンの主演男優賞受賞を邪魔したエドワード・ノートンもいる中、それどころじゃないすごさだった。 とにかくよく書かれた、先の展開の予想をどんどん裏切っていく脚本の中で、くるくると存在感を変えていくハートマン、じゃなくてフレッチャーという男。そのジェットコースターのような「人格変化」ぶりをJ・K・シモンズは、顔のしわを巧みに利用して演じ分けていく。カメラが顔の一部分だけをとらえていても、その変化は見て取れるのである。見惚れてしまう。 アメリカ人は鬼教官物が好きだ。たいてい、未熟で鼻っ柱の強いけれど才能を秘めた若者をいちど地獄に叩き落としながら、救い上げ、鍛え上げて”トップガン”に育て上げる。優勝させたり、合格させたりして、強い父とそれを乗り越える息子という「父子のあるべき姿」のような関係を作り上げてめでたしめでたし、である。とくに近年、日本でもよく言われるように父権が弱くなり、友達のような親子関係が大切だとされる風潮の中で、男子はそれでは一人前の男になれないぞと言いたがる人々が存在するのである。女子、母親からすれば、ケッ、ってなもんである。がしかし、こういうストーリーは、けっこう気持ちを昂揚させてくれるのも事実だ。スポーツや軍隊を舞台にした物語が多いのは、勝ち負けがはっきりしていることと、それが生死につながることがあるから、だろう。 ことし30歳のデイミアン・チャゼル監督はこの物語を音楽の世界に持ち込んだ。いや、どんな世界でもこの鬼教官物は成立するのだろう。アメリカはなんでも競争、コンテスト、優勝者と敗者、一番以外はクズだという社会だから。 舞台は(主人公曰く)国一番の音楽大学、である。どうもニューヨークにあるようなのでジュリアード音楽院がモデルだろう。ジャズのドラマーを目指し入学した一年生19歳のニーマンが主人公である。二人暮らしの父方の家族は郊外の中流一族、おそらくユダヤ系の、は日本のことわざで言えば「鶏頭牛後」な人々である。父は物書きと自称しているが高校教師であり、その兄の一家は郊外の小ざっぱりとした家に住み息子たちは2流大学の弱いアメフトチームでナンバーワンを誇っている。音楽でナンバーワンになることなど、女々しく、アメリカの男として意味がないことだと考えている一家である。母はニーマンが子どものころに家を出た。父は優しい。母の役目も果たしながら良き友達のようにニーマンを温かく、自由に育ててくれている。ニーマンはそんな暮らしを受け入れていた。フレッチャーに出会うまでは…。 フレッチャーはニーマンを自分のバンドに抜擢する。それからニーマンはどんどん嫌な奴になっていく。フレッチャーに近づき彼の要求する演奏をするために、文字通り血を流しながら練習を重ね、音楽院のバンドの中という小さな世界でナンバーワンのドラマーとなるためにすべてをささげる。それでも、フレッチャーの要求は留まるところを知らない。そして…。 さて、ここからの展開がすさまじい。尊厳をかけた戦いが繰り広げられるのだ。人間として、音楽家として。その戦いはドラムセットに飛び散る汗と血潮、ニーマンの手元、ニーマンの顔、そしてJ・K・シモンズのしわで表現される。音・映像・演技の圧倒的な迫力を刻み込む編集がまたすごい。見終わって、どっと疲れる。どれだけ緊張して観ていたかを思い知る。そんな映画はそうそうない。『セッション』は音楽映画の、そして鬼教官物の新しいマスター・ピースになるだろう。
アネット・カーンが『Women's Cinema』第3章Textual Gratificationで指摘したように、70年代後半以降、支配的映画を製作・配給してきたハリウッド・メジャー映画会社にとって、支配的な映画の構造にある程度同化できると判断された"フェミニスト"映画は、支配的な映画のジャンルのひとつである"女性映画"の中に位置づけられ、一般公開されるようになってきた。『素晴らしき日』はまさにそんな”女性映画”の一本である。今ではジョージ・クルーニーの数少ないロマンチック・コメディの代表作だと言っていいだろう。 90年代初め、80年代ハリウッドの支配的な映画がティーンズ向けのSFX映画に占領されたことへのアンチテーゼのように、"女性映画”の復権がおこる。フェミニズム的視点から映画を分析する映画学者あネット・カーンの著書で指摘されたように、低予算の独立系映画が分化された観客に向けて作られるようになり、その中に「支配的映画が与えてくれる女性向き映画を好む」女性観客とともに、「フェミニズム的思考を持つ」女性観客もいたのである。 しかし、80年代までエグゼクティブを男性が占めてきたハリウッド・メジャー映画会社ではこの分化された女性観客に対処することはできなかった。1990年、ディズニーの系列会社タッチストーンのプロデューサーであるローラ・ジスキンがエグゼクティブ・プロデューサーを務めた『プリティ・ウーマン』がスター・バリューを越えた大ヒットを記録し、女性観客の存在をハリウッド・メジャー映画会社に印象づけたことをきっかけに、この分化された観客の動向をおそらく知るであろうと、各スタジオで女性エグゼクティブの起用や、女性の独立系プロデューサーの起用がブームになった。そして、1995年、フォックス2000の社長に就任したローラ・ジスキンがゴー・サインを出した作品のうちの一本がこの『素晴らしき日』であった。 各社の女性エグゼクティブたちは女性監督や独立系女性プロデューサー、女性脚本家を起用し、女性映画人への門戸を押し開いていく。この女性映画人たちは70年代のフェミニズムの時代を、映画を作りたいという希望を胸に、大学の映画学科に学んだり独立プロのスタッフとして経験を積んできた人々である。彼女たちが作りだした"女性映画"が、必ずしも"フェミニスト映画"ではなく、"チック・フリックス"や"支配的な映画が与えてくれる女性映画"であったとしても、その志には"フェミニズム"的考え方があったのである。 例えば『素晴らしき日』の原案・プロデュースを務めたリンダ・オブストは1950年ニューヨーク生まれ。ニューヨーク・タイムスの編集者やローリングストーン誌の記者を経てロサンジェルスに移り、デビット・ゲフィンの会社のスクリプト開発係(d-girlと呼ばれる脚本下読み係)から映画製作者になった人。『フラッシュダンス』の脚本開発から始めて、ジョン・カーペンターとのコンビで知られる女性プロデューサーのデボラ・ヒルと組んでプロダクションを作り『フィッシャー・キング』などをヒットさせた。90年半ばから後半は、30代になった人気"ロマ・コメ"女優たち(眼具・ライアン、サンドラ・ブロック、ミッシェル・ファイファーなど)が自ら製作プロダクションを作って出演作の開発をした時期であり、オブストはそんな女優たちのパートナーとしてプロダクションを立ち上げたり、映画製作まで世話することも多かった。『素晴らしき日』にはミッシェル・ファイファーがエグゼクティブ・プロデューサーとして名を連ねており、ファイファーの個人プロダクションも製作に一枚かんでいる。 70年代にリベラルな大学生時代を過ごしたオブストにとって、女性がリーダーシップをとる映画作り、また女優がメインになる映画作りは一つの夢であった。女優が30歳をすぎると演ずる役がなくなってしまうようなハリウッド、女性が犠牲的な役柄しか与えられないハリウッド、仕事も結婚や子育てと同じように女性にとって大切だという考えが反映されないハリウッド、そんなハリウッド映画を自分たちの仕事で変えたいと考えていたのである。 ハリウッド映画で女性が活躍していた20年代~30年代、女性脚本家たちがよく手掛けていたソフィスティケイテッド・コメディのスタイルを彷彿とさせる『素晴らしき日』はそんなオブストの夢を実現した作品であった。 もちろん、カーンが批判するように、この支配的な映画ジャンルとしての"女性映画"への"フェミニスト的映画"の吸収は、"フェミニスト的主張を映画を使って前景化したい女性映画人"と"まずは映画界に地歩を築くこと、すなわち興行的な成功を目指して、フェミニスト的主張は前景化しない女性映画人"に、映画作りを目指す女性たちを分断することになったのも確かだ。90年代、ハリウッド・メジャー映画会社が女性映画人を起用し、支配的な映画の一ジャンルとしての"女性映画"および"チック・フリックス"を作らせていたのに対し、ニューヨークを起点とするインディペンデント映画を作る女性映画人たちは「ウーマン・メイク・ムービー(WMM)」を結成、"フェミニズム映画"や"インディペンデントな作家映画"を発表した。ふたつのグループを行き来する監督もまれにいたが、カーンの危惧したようにハリウッドとインディペンデントの溝は、女性映画人たちの"シスターフッド"を持ってしても埋めることはできなかったようだ。2000年代に入ってハリウッドの"支配的映画"界で生き残ったのは、"支配的な映画の与えるジェンダー・バイアス"を自分のこととして受け入れる保守的な女性監督であるか、"フェミニズムとも関係ない作家性"を"支配的な映画"の主観客である男性観客が好むジャンルに対して発揮する監督であった。"フェミニスト的"女性製作者はその主張をさらに後景化させ、生き残りを図ったが、"フェミニスト的"女性監督たちはその活動の場をハリウッドやニューヨークのスクリーンからテレビに移動させたのである。 ● アネット・カーン的解釈における古典的語りの方式映画としての『素晴らしき日』 『素晴らしき日』はフェミニズム的女性映画人(監督は男性ではあるが、"女性映画"を手掛けることも多い人である)たちの作品ではあるが、"フェミニズム"を前景化しない"女性映画"として作られている。より多くの観客、おそらくそのほとんどは女性であると考えられるが、に見てもらい、共感を得るための方法である。 そのため、一日の出来事であるストーリーは時系列でスムーズに流れ、プロットはわかりやすく整理されている。二人の大人が、別々の場所で別々の仕事をこなしながら、という設定なので、クロス・カッティングを巧みに使い、別々の場所で起こっている物事をそれぞれの当事者を主体とした語りで交互に見せるという工夫がなされている。別々の場所で別々の仕事をこなす二人は、終盤になって二人で同一の場所に向かい、二人で力を合わせて難局を乗り越える。シングル父ジャックにとっては、前妻に「無責任」と言われた"親性の"「欠如」を補い、シングル母メラニーにとっては強すぎる「責任感」のための"ゆとり"の「欠如」を、そしてメラニーの息子にとっては「父の欠如」を補う、新しいパートナーであることが示されていき、二人の間に親密性が生まれる。 携帯電話の交換など、離れている二人が互いの事情を知ることになる仕掛けもあり、携帯での会話シーンはスプリット・スクリーンによって処理され、顔を合わさずに掛け合いが観客には楽しめるようにしてある。観客は、トドロフの言う「後ろからの視線view of behind」の持ち主として、メラニーに、またはジャックに寄り添い、別々に行動する二人を見て、同時にそこにはいないもう一人の行動と次の予定、またはその予定を変えざるを得ない事情、その事情によって変化していくであろうもう一人の行動予定、そしてそれが引き起こすであろう二人の混乱を予想するのである。さらに、観客は互いに相手がいないときに子どもたちから情報を得て、相手の好意の在り方を探る二人を知っている。つまり、当人たちは不安を持ちながらも相手に魅かれつつあることを知るのは観客だけなのである。力を合わせて難局を乗り越えた時、二人のキャラクターとしての諸事情は、恋に落ちた二人というテクストの流れに縫合され、ストーリーは大団円を迎える。 『素晴らしき日』のカメラはミディアム・ショットを主とし、クロース・アップの使用はスター映画にしては控えめである。ロング・ショットは舞台となるニューヨークという街を生かすため空撮を交え、特色ある街の一部を入れ込むために使われる。90年代のロマンチック・コメディのヒロインは都会で働くキャリア・ウーマンであることが多く、その存在が自然に受け入れられる場所、もしくはキャリア・ウーマンを目指す若い女性が憧れる街として、ニューヨークという街が舞台にされることが多かった。『素晴らしき日』の場合、メラニーが務める建築設計事務所はロックフェラー・センターにあり、ジャックが務めるニューヨークタイムズ新聞社は43丁目と、マンハッタンのミッドタウンにある。二人、もしくは子どもたちを含めた四人は、タクシーや徒歩でミッドタウンを走り回る。子どもが一緒の場合、ショットは子どもたちを入れ込むため大人の膝を入れるくらいのサイズまでカメラがひかれ、ほぼ全身が入るショットになってしまう。それに対して大人二人のロマンチックなシーンは二人のバスト・ショットと、クロース・アップで構成される。最初に二人が画面に登場する際のバスト・ショットは、双方ともまったく構えていない、パジャマ姿であるが、それでも十分に観客にとっては美女と美男であることがアピールされる。二人が初めて顔を合わせるシーンは子どもたちの学校の閉められた扉の前だが、そこでは子ども入りのミドル・ショットから、二人がそれぞれに離婚した前の結婚相手の嫌な部分を互いにイメージするバスト・アップへと切り替わる。この後、バスト・ショットで登場するたび二人は言い合いになり、ウイットにあふれた会話の戦いを繰り広げることになる。観客はラスト・シークエンスにいたっても、十分に惹きつけられあって、それを自覚しながらも意地を張り合うふたりのバスト・ショットを、じりじりしながら見せられ、やっとふたりがキスをする段になってクロース・アップされていくカメラにほっとする。が、そこに「ママ!」と呼ぶ息子の声で恋人たちは親であるというミディアム・ショットの現実に引き戻される。ラブ・ストーリーとファミリー・ドラマが縫い合わされるわけだ。 ● 視覚快楽装置としての『素晴らしき日』 また、『素晴らしき日』はカーンの言うLookについても考察を加えることのできる映画である。カーンはマルヴィを引き、支配的な映画は男性を観客として設定するため、女性キャラクターは男性観客に視的快楽を与えるためのスペクタクルとしてしか描かれないことを示唆した。しかし、『素晴らしき日』の主役はあくまでもミッシェル・ファイファー演ずるメラニーであり、ジャックは女性観客とメラニーのためのスペクタクルである。女性観客に対して、支配的な映画における"女性映画"はしばしば女性の社会的役割、バイアスのかかったジェンダーを押しつけるための装置として働かされてきた。そこから逸脱する女性は罰せられる、と暗に描かれてきたものだ。その仕組みを90年代の支配的映画のジャンルとして"女性映画"を作る"フェミニズム的女性映画人"たちは変えようとする。 メラニーは上流階級の出身だが、母や妹のように同じ階級のつまり金持ちの妻になり、社交が仕事と考えるような"保守的"で"恵まれた・幸せな"暮らしを拒否した女性である。進学し手に仕事を持ち一流の会社に入ってキャリアを積みつつ、自由な恋愛(母親や妹は絶対選ばない男との!)、金よりも夢を追う男との恋を選び、結婚し出産。けれど、この夢を追う男は子どもを一緒に育てるよりも自分の夢だけに目が向いている大きな子どもでしかなく、離婚。仕事も子育ても一人でやってみせるときりきり舞いの日々。とにかくキャリア・アップすれば、給料も増えるのでシッターを雇うこともできるようになると、まずはキャリア・アップを優先している女性である。 子育てよりキャリア。それを『素晴らしき日』は否定しない。しかし、キャリアのために子どもを犠牲にしない方法を模索する。母親であることもキャリア・ウーマンであることと同じくらいに素晴らしいことだと描く。その方法は親が二人で責任を持って子育てすること。そのためにはもう自分の夢だけ追いかける子どものままの"ピーターパン"男は願い下げ、なのだ。そこに現れたジャックが言う「おふくろは"子ども心をもった男と結婚しろ"と言っていたぜ」。メラニーの答え「あなた、ゲイ?」 もちろんそういう意味ではない。ジャックは会社中の女が狙っているようなセクシーな二枚目である。特ダネを狙う新聞記者という仕事柄時間は不規則だし給料も高くはない、部屋の片づけや着るものにも頓着しない、子どもに対して大人として接するより対等な人として(どちらかというと子どもとして)接する。それが前妻には無責任でだらしのない男と映り離婚された(たぶん彼女が再婚したのはもっと稼ぎのいい堅い仕事の男なのだろう)。けれど、ジャックは信念の人なのである。市長とマフィアの癒着と公務員の汚職を暴こうとしている。実は子ども好きで、時間が許せば子どもといたいし、子どもの気持ちを理解できる大人である。メラニーに欠けているのは、一生懸命すぎて、子どもは思いのままにはならないということを理解できないというところなのだ。 メラニーの計画性とジャックの包容性。男は計画的でアグレッシブ、女は感情的で受動的というジェンダー・バイアスとは逆の性格設定である。二人は大変な一日を、ふたりでいやいやながら融通しあい、協力してのりきっていくうち、自分に欠けているものに気付き、それを補うものがこの人にあることに気づいて、最初に持ったイメージを訂正していく。そして、子育てをともにするパートナーとして、かつ、魅力的な恋人として意識していくのである。 二人の性格や立場、子どもとの関係を表現するミゼアンシーン、演出は衣装や小道具などにも現れている。"昔ながらの新聞記者"スタイルでノーネクタイ・ツイードのジャケット・クシャクシャのコートというジャック。彼はかばんすら持っていない。一方メラニーはグレーのスーツにパンプス(ヒールは中くらいで太く、実用的。このまま子どもを追いかけて走れる靴である)。大きなカバンからは魔法のように仕事周り・子ども周り、どこで何が起きても大丈夫なようにいろいろな物が出てくるのだ(そして期待通りいろいろなことが起きて、メラニーの勝負ブラウスはジュラシックパーク柄の子ども用Tシャツに変わってしまう)。 女性にとってメラニーになることは難しくない。キャリアも家庭も子どもも全部手に入れるために頑張ろうと思い、努力する女性は80~90年代にかけて、アメリカでも日本でもたくさん育ったはずだ。が、それに対して男性の意識変革は遅々として進んでいなかったのが現実だったのだろう。現実にいないのはジャックのような男なのである。それをジョージ・クルーニーは鮮やかに体現して見せた。すべてをアグレッシブに望む女性たち、キャリア・ウーマンである女性観客にとって、ジャックは夢の男、スペクタクルであった。(実際に『アウト・オブ・サイト』で98年にジョージ・クルーニーが初来日した時、インタビューにやってきたのは女性誌の編集長や副編集長という30代のキャリア・ウーマンたちだったという。いつもならライターや編集部員がこなすはずのインタビューである。宣伝部の人々は不思議がっていたが、さもありなんと私は思ったものだ) 映画が女性の、フェミニズム的視線で作りかえられるとき、その視覚快楽の対象、窃視症の対象は、男性主体のそれとは変わる。そんな時代がすくなくとも90年代にはあったのである。