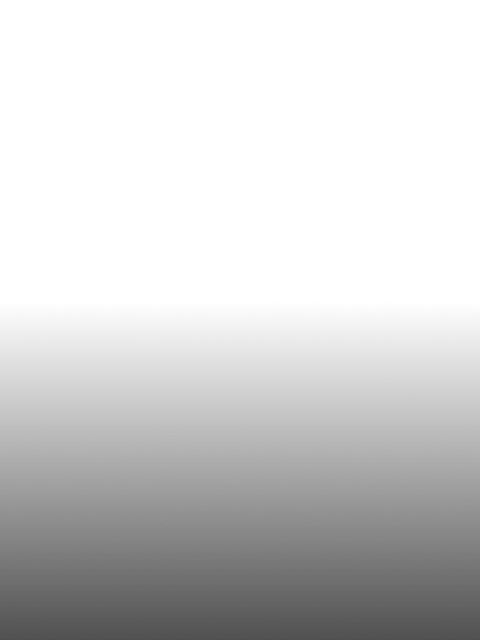利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧にはシネフィル アジアへのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
いくつかの映画祭で一次審査に加わっている。日本の作品を見ているとプロが応募してくるものはさておき、どうも「音」についてのいい加減さが目に、いや、耳につくことが少なくない。 フィルムの場合、音は後からつけるものであった。同時録音で現場の音を取っておいても、それは音素材の一つであり、それを調整してセリフと合わせ、さらに作られた音を加えて映画の音は出来上がるものだった。 しかし、デジタル機材が発達し、その機材で撮られた音も十分に使えるレベルのものになったとき、つい、音は映像と対になっていると安心してしまい、音をどう使うかを考えずに作品化してしまうのである。 音は一つの表現を持つ素材である。どこに、どんな音を使うか、それはどのくらいの大きさで、どこから流れてくるのか。その音が「表すもの・こと」は何なのか。それを考えて作られた映画は、厚みが違う。それは劇映画だけではなくドキュメンタリー映画でも同じである。この話はまたいつかしよう。 さて。こんなことを考えたのは『イマジン』という作品を見たからだ。 『イマジン』は盲目の子どもたちが学ぶ学校にやって来た「反響定位」法の教師と子どもたちや若者、そして引きこもっていた盲目の女性との交流を描く。ラブ・ストーリーでもある。子どもたちは実際に目が不自由な素人をキャスティングしており、各国から集められた子どもたちは、英語・フランス語・ポルトガル語を話している。「反響定位」法とは、物・人・自分が出す音とそれが反響する音を聞いて自分の位置を知ったり物や人の位置を知ったりするという方法である。この方法を身につければ、白杖を持たずに外出することもできる、という。特殊な才能ではあるが、訓練を積めばある程度は取得できる方法でもあるらしい。しかし、日本など多くの国では、視覚障碍者が白杖を持たないで外出をすることは本人にとって大変危険であるということで禁止さえされているのが実情である。 舞台になっているのはポルトガルの視覚障碍者のための診療所で、監督はポーランド人。主役の男性教師はイギリス人俳優でヒロインはドイツ人女優である。共通語として英語のセリフが多いが、この映画の場合、大切なのはセリフや言葉より「音」なのだ。それを際立たせるためもあっての多国籍化ではないかと思う。 そう気づけば、あとは耳を澄ますしかない。観客にはすべてが見えている。そう思うのが、映画のマジックの一つである。登場人物の知らないことも観客には知らされているので、観客は登場人物たちの先回りをしてハラハラすることを楽しむのが古典的映画のセオリーの一つだ。 そのマジックを『イマジン』は引きはがす。観客も登場人物と一緒になって、あらゆる「音」を聞き、想像していかなければならない。そうでないと真実には到達できないのである。澄ますのは耳だけではない、観客には感じることのできない、匂いや太陽の温かさにも敏感にならなければいけないのだ。登場人物が感じているたろう現象を、観客は映像をもとに想像しなければいけない。そうして初めて「見えてくる」のが『イマジン』という映画である。 「音」というものの情報量の豊かさ、種類の豊富さ、意味などをこれだけ豊かに使って聞かせて見せた映画も少ない。そのアイデアに、まだまだ映画ができることは多いのだと気づかされもする一本である。
アカデミー助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズ。スキンヘッドにムキムキ筋肉の腕、逆三角体型に、黒のシャツとジャケット。とても音楽大学の教師とは思えないキャラクターつくりなのだが、彼の登場シーンみっつめでその理由がわかる。 『セッション』は『フルメタル・ジャケット』なのだ。シモンズ演ずるフレッチャー教授はハートマン軍曹なのである。監督もそのつもりで描いたという。なるほど、そのあたり、若い監督はバレバレに作っちゃうのだな。 サンダンスでグランプリや観客賞を獲った作品はカンヌのある視点部門か監督週間に登場するのが常なのだが、サンダンス映画祭ダブル受賞の『セッション』も当然カンヌで上映された。が、残念ながら見逃していたんだよね。で、メイン・コンペの『フォックス・キャッチャー』を見て、スティーブ・カレルのアカデミー賞”助演男優賞”を確信したわけだ。ま、色気を出して”主演”ノミネートにした時点でそれはちと無理、とは思ったが、「助演だったらとれたのに…」と私はまだ自分の予想に未練を持っていた。『セッション』を見るまでは。 J・K・シモンズはすごい。すごかった。助演男優賞ノミニーには『バードマン』で主役を食ってしまってマイケル・キートンの主演男優賞受賞を邪魔したエドワード・ノートンもいる中、それどころじゃないすごさだった。 とにかくよく書かれた、先の展開の予想をどんどん裏切っていく脚本の中で、くるくると存在感を変えていくハートマン、じゃなくてフレッチャーという男。そのジェットコースターのような「人格変化」ぶりをJ・K・シモンズは、顔のしわを巧みに利用して演じ分けていく。カメラが顔の一部分だけをとらえていても、その変化は見て取れるのである。見惚れてしまう。 アメリカ人は鬼教官物が好きだ。たいてい、未熟で鼻っ柱の強いけれど才能を秘めた若者をいちど地獄に叩き落としながら、救い上げ、鍛え上げて”トップガン”に育て上げる。優勝させたり、合格させたりして、強い父とそれを乗り越える息子という「父子のあるべき姿」のような関係を作り上げてめでたしめでたし、である。とくに近年、日本でもよく言われるように父権が弱くなり、友達のような親子関係が大切だとされる風潮の中で、男子はそれでは一人前の男になれないぞと言いたがる人々が存在するのである。女子、母親からすれば、ケッ、ってなもんである。がしかし、こういうストーリーは、けっこう気持ちを昂揚させてくれるのも事実だ。スポーツや軍隊を舞台にした物語が多いのは、勝ち負けがはっきりしていることと、それが生死につながることがあるから、だろう。 ことし30歳のデイミアン・チャゼル監督はこの物語を音楽の世界に持ち込んだ。いや、どんな世界でもこの鬼教官物は成立するのだろう。アメリカはなんでも競争、コンテスト、優勝者と敗者、一番以外はクズだという社会だから。 舞台は(主人公曰く)国一番の音楽大学、である。どうもニューヨークにあるようなのでジュリアード音楽院がモデルだろう。ジャズのドラマーを目指し入学した一年生19歳のニーマンが主人公である。二人暮らしの父方の家族は郊外の中流一族、おそらくユダヤ系の、は日本のことわざで言えば「鶏頭牛後」な人々である。父は物書きと自称しているが高校教師であり、その兄の一家は郊外の小ざっぱりとした家に住み息子たちは2流大学の弱いアメフトチームでナンバーワンを誇っている。音楽でナンバーワンになることなど、女々しく、アメリカの男として意味がないことだと考えている一家である。母はニーマンが子どものころに家を出た。父は優しい。母の役目も果たしながら良き友達のようにニーマンを温かく、自由に育ててくれている。ニーマンはそんな暮らしを受け入れていた。フレッチャーに出会うまでは…。 フレッチャーはニーマンを自分のバンドに抜擢する。それからニーマンはどんどん嫌な奴になっていく。フレッチャーに近づき彼の要求する演奏をするために、文字通り血を流しながら練習を重ね、音楽院のバンドの中という小さな世界でナンバーワンのドラマーとなるためにすべてをささげる。それでも、フレッチャーの要求は留まるところを知らない。そして…。 さて、ここからの展開がすさまじい。尊厳をかけた戦いが繰り広げられるのだ。人間として、音楽家として。その戦いはドラムセットに飛び散る汗と血潮、ニーマンの手元、ニーマンの顔、そしてJ・K・シモンズのしわで表現される。音・映像・演技の圧倒的な迫力を刻み込む編集がまたすごい。見終わって、どっと疲れる。どれだけ緊張して観ていたかを思い知る。そんな映画はそうそうない。『セッション』は音楽映画の、そして鬼教官物の新しいマスター・ピースになるだろう。
『インタースティラー』35mmフィルムで新宿ミラノ最終上映なんですか。寂しいけれど、あの大画面の最後にふさわしい作品ですね。 こういう大作になるとプロデューサーが何人もクレジットされます。製作総指揮、製作というクレジットで。 今回その中に見つけたのが リンダ・オブスト という名前でした。 映画が進むうち、ははぁ~ん、なるほどと納得。 以降、なにがあってもびっくりしなかったもんね。 いや、びっくりする展開であったけれど。 と、いうのも、リンダ・オブスト って『コンタクト』のプロデューサーなんですね。 もともと雑誌の編集者で、その後いくつかの単行本をヒットさせ、映画にかかわることになった人なんですが、彼女は『コンタクト』のアイデアのもとになったカール・セイガンの本を出しているんですよ。セイガン夫妻に信頼されて、いろいろと互いに協力していた、という過去があるんです。 プロデューサーとしてテリー・ギリアムの『フィッシャー・キング』をヒットさせたり、サンドラ・ブロックのラブコメを手掛けサンドラのプロダクションを手伝ったりと、90年代後半の女性映画人ブームの立役者の一人でした。この時期の女性映画人たちはシスターフッドというか横のつながりが強くて、互いに協力し合っていたんですね。監督でもありプロダクションを持っていたジョディ・フォスターもそんな一人で、それで『コンタクト』を手掛けたんだと思います。 そのころサンドラとともに『評決のとき』に出て人気の出たマシュー・マコノヒ―が『コンタクト』にもでて、リンダ・オブストと知り合い、その縁が今またつながったのかなと思います。 で、『インタースティラー』。『ゼロ・グラヴィティ』のヒットが追い風になったと思いますが、話の展開は『コンタクト』に近いですもんね。 ネタバレはしない方がいい作品なので、この辺でやめておきますが、『インタースティラー』見た後『コンタクト』を見直してみてください。たぶん、なるほどね、と思っていただけると思います。で、この二本をつなぐのがリンダ・オブストとカール・セイガンなんですね。と、わたしはナットクしております。